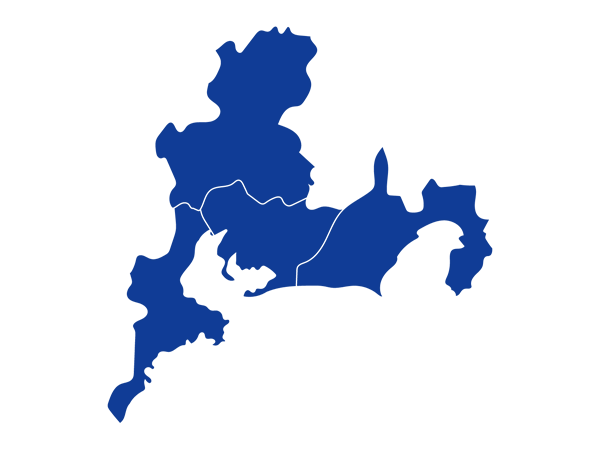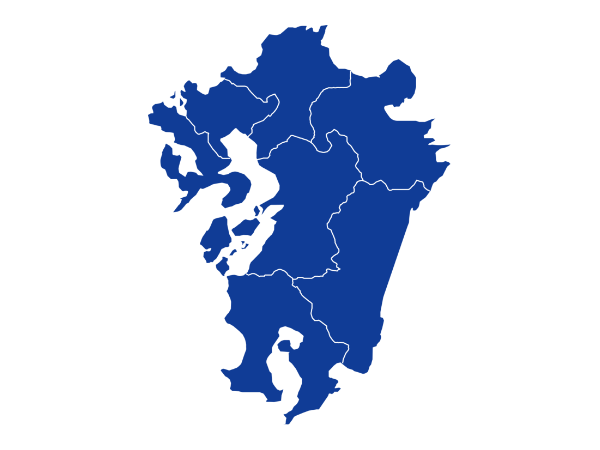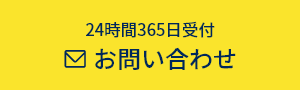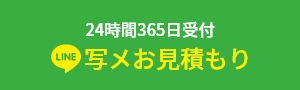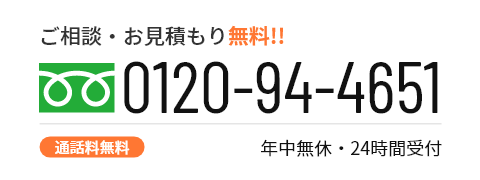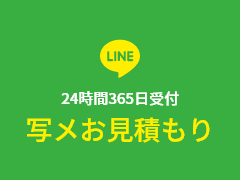火事は、私たちの生活を一変させてしまいます。被害を受けた直後は、気が動転し何から手をつければいいのか分からなくなる方も多いでしょう。
しかし、火事の後には「罹災証明書の取得」や「火災保険会社への連絡」等すぐにやらなくてはいけない重要な手続き等がいくつもあります。
この記事では、火災後の初動対応から業者による実際の復旧作業の手順、注意点までを分かりやすく解説しています。
大切な暮らしを取り戻すために、正しい知識を身につけておきましょう。
目次
火災後にやるべき重要な手続き

まずは火事後にしなければいけない手続きについて解説します。
罹災証明書の取得
罹災証明書とは
市区町村が「火災によって被害を受けた」ことを証明する公的な書類で、
保険請求や公的支援の申請、税の減免などに必要です。
■取得の流れ
まずは、市区町村役所に連絡し「罹災証明書の申請をしたい」旨を伝えます。
↓
現地調査の手配
被害状況を確認するため、役所の職員が現場を調査します。
※片付けは調査が終わるまで控えること
↓
写真の保存
自分でも撮っておくことをおすすめします。
(被害箇所の写真を複数角度で残す、家財の写真も撮っておく)
↓
証明書の発行
現地確認の後、罹災証明書が発行されます。(数日~1週間程度)
■必要書類■
□本人確認書類(免許証など)
□火災の場所の住所が分かる書類
□火災出動証明書(消防署で取得できることも)
※自治体により異なる場合があるので要確認
保険会社への連絡と手続き
火災保険を利用する場合、被害状況を保険会社が確認する前に片付けてしまうと、補償が受けられないことがあります。必ず先に連絡をしましょう。
■手続きの流れ
加入している保険会社にすぐ連絡
火災が起きたこと、被害の範囲、契約者情報(証券番号など)を伝えます。
↓
必要書類の確認
・保険金請求書
・罹災証明書(自治体で取得)
・被害写真(自分で撮影)
・修理見積書(必要に応じて)
↓
保険会社の調査
鑑定人が被害状況を確認するので、それまで片付けは控えてください。
↓
保険金の請求・支払い
書類がそろえば、審査後に保険金が支払われます。
<<ワンポイント>>
電話連絡後、メールやアプリなどで進捗管理ができる保険会社もあります
片付け後の証拠が足りないと「全損」扱いにならないこともあるので注意
ライフラインの停止手続き
火災が発生した場合、ガスに関しては消防署からの通報があれば、自動的に供給が停止される仕組みになっています。
しかし、その他のライフラインについては、火災にあったからといって自動で止まることはありません。
そのため、被害状況に応じて自身で各サービス会社に連絡し、停止の手続きを行う必要があります。
罹災直後~数日以内に連絡しましょう。
・電気
・ガス(都市ガス or プロパンガス)
・水道
・インターネット・固定電話など
※ライフライン業者によっては、被災者支援措置(基本料金免除など)がある場合も
火災後の片付け手順と注意点
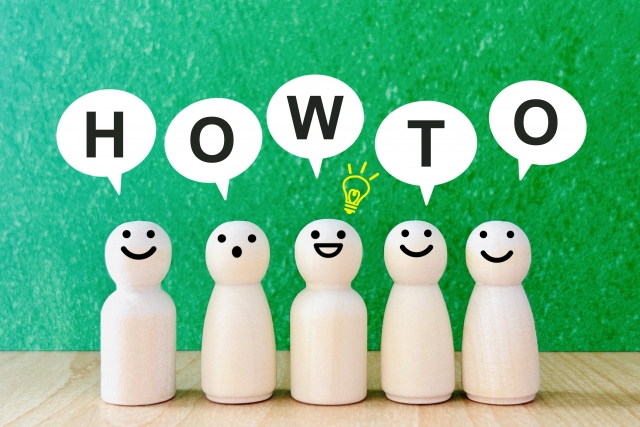
ここからは、弊社で施工した実際の火災復旧作業を元に、家事の片付け手順や注意点を紹介します。
【実例】和歌山県新宮市・全焼の場合
火災によって家が全焼した場合、建物や家財はほとんど残らず、個人で対応することはほぼ不可能です。
そのため、火災後の片付けや撤去作業は、専門の業者に依頼するのが一般的です。
作業にかかる時間や費用感なども参考にしてください。
<<ご依頼内容>>
マンションの一室で火災が発生し、室内には燃えた家財や大量の煤(すす)が残っているため、
解体工事から消臭作業まで一貫して対応してほしい
現場を確認したところ、すべての部屋に煤(すす)や燃えた家財の残骸が散らばっている状態でした。特に和室とリビング部分の被害が大きく、壁や天井には一面にスス汚れが広がっていました。
これは、火が出てから鎮火するまでに時間がかかると、あっという間に炎が家中へ広がってしまうためです。
火は下から上へと燃え広がる性質があるため、小さな火災(ボヤ)であっても、周囲の壁や天井には必ずススが付着してしまうのです
<<作業前の準備>>
□管理会社への事前許可取得
□近隣住民への事前周知(ビラ配布など)
□廃棄物の処理方法確認(市町村ごとに異なるため)
□作業計画の立案とスタッフ配置
<<作業内容>>
※火災保険に入っていなかったため、今回は煤清掃を行わず解体工事までの作業
・養生作業
作業開始前に、建物の共用部分や通路などをしっかり保護します。
↓
・スケルトン解体工事
建物の構造部分(柱や梁)だけを残し、内装をすべて撤去する工事です。
火災現場では、壁や天井、床材の奥まで煙や臭いが染み込んでいるため、スケルトン状態にしないと臭いを完全に取り除くことができません。
↓
・有害物質除去作業
火災によって発生した煤(すす)や焼けた建材には、有害物質が含まれていることがあります。
特に古い建物ではアスベストが含まれているケースもあるため、専門知識と装備を持つスタッフによる安全な除去作業が必要です。
↓
・残置物撤去
燃え残った家具や家電、日用品などを丁寧に分別・撤去します。
↓
・消臭作業
最後に、tな機材や薬剤を使って消臭作業を行います。
火災特有の焦げ臭や煙臭は、通常の清掃では完全に取り除けないため、オゾン脱臭や薬剤噴霧など、プロによる専用の作業が必要です。
被害の程度に応じて、複数回に分けて消臭を行うこともあります。
<<基本情報>>
間取り:2LDK(マンション一室)
作業日数:3日間(計約18時間)
作業人数:15名
作業金額:1,076,350円(税込)
火事後の片付けにおける注意点
<<作業前の注意点>>
□管理会社へ許可を頂きビラ等の配布で周知する・・・スタッフの出入り、騒音などのトラブルを防止。
□燃えゴミの処分場所を各市町村へ事前確認・・・廃棄物はきっちり分別して定められた場所へ。
確認を行わないままにしていると、結果的に工期が伸びてご依頼者様への負担が大きくなってしまいます。
<<その他注意点>>
□経験豊富なスタッフを配置する・・・火災復旧作業は煤清掃のほか解体工事も行うのでスキルが必要です。
□残置物の仕分けは慎重に・・・火災によって燃えた貴重品などを見落とさないよう慎重に仕分けを行わなければいけません。
□火災復旧作業には許可証が必要・・・都道府県知事から許認可を受けた許可書を保持しているか(解体工事業、内装仕上げ工事業、塗装工事業など)
※許可証を持たない業者が作業を行うことは違法となります。
上記の内容は火災復旧作業を業者へ依頼する際、業者選びの目安となりますので、ぜひ参考にしてくださいね。
火事の後片付けならお任せを

本記事では、火事の後片付けってどうしたらいい?重要手続きや具体的手順を解説という部分に焦点を当てて解説しました。
【内容まとめ】
・火災後に必要な手続き 「罹災証明書を取得」「火災保険会社に連絡」「ライフラインの停止」
・専門業者による復旧作業の流れ
・片付け作業の注意点
火災復旧についてお悩みでしたら、プロである私たち業者にまずはお気軽にご相談くださいませ。
現在悩まれている方にとって本記事の内容がお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。