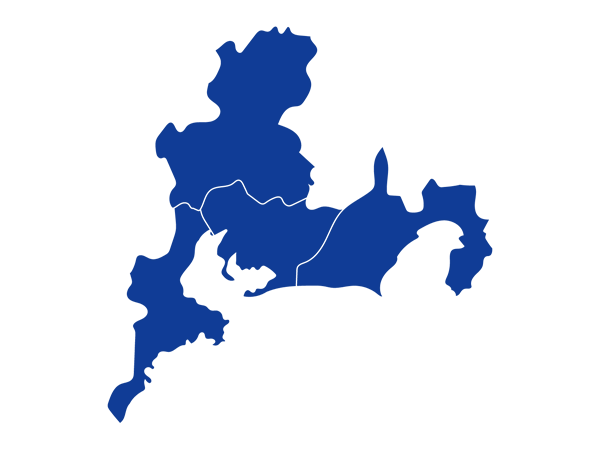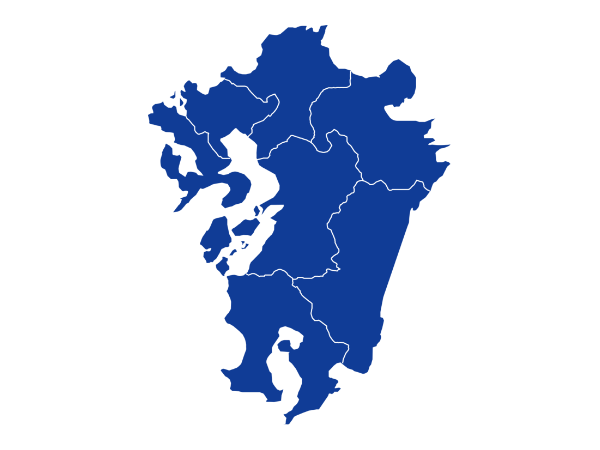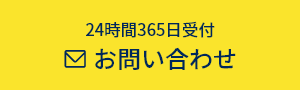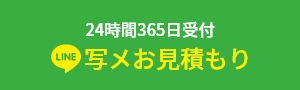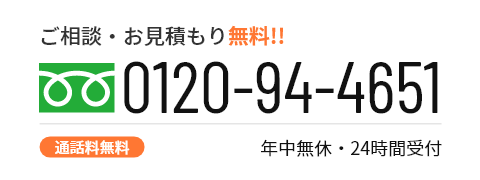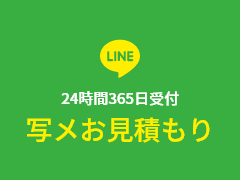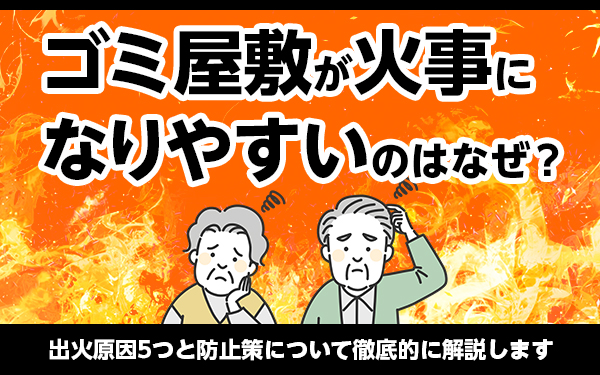
「ゴミ屋敷」は、衛生面だけでなく火災のリスクが非常に高いということをご存じでしょうか。
大量の可燃物が屋内外に蓄積された「ゴミ屋敷」は、一度火がつけば一気に延焼してしまう危険性があるのです。
実際、ゴミ屋敷から出火した火災が、近隣住宅への延焼や人命被害にもつながってしまうケースも報告されています。
今回は、ゴミ屋敷のよくある出火原因や、火災を未然に防ぐために取るべき具体的な防止策等について紹介します。
ゴミ屋敷火災の出火原因5つ

ゴミ屋敷火災の出火原因には、日常生活の中に潜む「ちょっとした火種」がゴミに引火し、大火災へと発展するケースが多く見られます。
以下に、代表的な火事発生の原因を紹介します。
1. タバコの不始末が起こりやすい
吸い殻を完全に消さずにゴミの上に捨てたり、灰皿の中の吸い殻が山積みになっていたりすると、残った火種が紙くずや衣類などに燃え移る可能性があります。
そうなった場合、ゴミ屋敷には可燃物が多く密集しているため、火がすぐに広がってしまいます。
2. 電気コードがショートしやすい
ゴミに埋もれた延長コードや電化製品の電源コードが踏みつけられたり、圧迫されたりして断線し、ショートや発熱を起こすことがあります。
また、コードの上に布や紙が覆いかぶさっていると、放熱できずに熱を持ち、それが火災の原因となることもあります。
3. コンロやストーブの近くに可燃物がある
可燃ごみがキッチンや暖房器具の近くにあると、調理中や暖房中に火が移りやすくなります。
特に、ストーブの上に洗濯物や紙が置かれていたり、ガスコンロ周辺に新聞やプラスチック製品が置かれていたりすると、わずかな火でも延焼します。
4. 自然発火・化学反応
ゴミ屋敷では、スプレー缶、電池、油、ペンキなどの危険物が分別されずに積み重なっていることがあり、それらが化学反応を起こして自然発火するリスクがあります。
特に高温多湿の環境では、こうした反応が起きやすくなります。
5. 放火・いたずらのターゲットになりやすい
ゴミが庭や路上、玄関先に大量に放置されていると、放火犯にとって「火をつけやすい環境」となり、狙われやすくなります。
実際、ゴミ屋敷への放火による火災事例は少なくありません。
見た目の異常さが目立つことで、標的になってしまうこともあるのです。
ゴミ屋敷になるのはなぜ?住人の心理

ゴミ屋敷とは、そもそも、住居内や敷地内に大量のゴミや不要物が長期間にわたって放置され、日常生活に支障をきたしている状態のことを指します。
具体的には
・食べ残し、腐敗した食品
・コンビニ弁当の容器、カップ麺のカップ
・ペットボトルや空き缶・空き瓶
・レジ袋や紙袋
・トイレットペーパーの芯や使用済みの衛生用品
・壊れたテレビ、電子レンジ、冷蔵庫などの家電
・本、雑誌、漫画など読み終えたものが大量に山積み
・ペットの排泄物やトイレ砂(未処理のもの)
等が、家中に溜まっている状況です。
ゴミ屋敷の住民には、「だらしない」「片づけができない」といったイメージが持たれがちですが
実は、その背景には複雑な心理や事情が隠されていることが少なくないのです。
ここからは、ゴミ屋敷住民の心理について詳しく解説します。
ゴミ屋敷住人の心理とは?
ゴミ屋敷になってしまう背景には、様々な事情や理由があります。
多くの人は、物を「不要」と判断できず過剰に所有し続ける傾向があり、これは「ホーディング(ため込み症)」と呼ばれる心理状態によるものです。
「いつか使うかもしれない」「捨てるのはもったいない」といった思考にとらわれ、物への愛着や不安、後悔の感情が強く働いています。
ゴミ屋敷化の背後には、家族や近隣との関係が希薄であったり、社会的に孤立していたりすることも多く、周囲に注意してくれる人がいないことで、自分の生活環境の異常に気づけないまま悪化していくケースも見られます。
その他、失業や離婚、家族の死などがきっかけで精神的なバランスを崩し、うつ状態に陥ることで片付ける意欲や気力を失ってしまう人もいます。
このような場合、「片付けられない」のではなく、「片付ける力が残っていない」ことが多いのです。
また、ゴミ屋敷の住人は、現実の問題に向き合うことを避けるため、あえて片付けを後回しにし、「今のまま」が最も楽で安全だと感じている場合もあるのです。
こうした心理的背景を理解することは、単なる「だらしなさ」ではないゴミ屋敷問題の本質を見極めるうえで非常に重要です。
ゴミ屋敷火災を防ぐための対策

以上のことからおわかりいただけたかと思いますが、ゴミ屋敷による火災を防ぐには、
本人の努力だけでは限界があります。
物を手放せない心理的なハードルや、体力・気力の問題を抱えている可能性が高いということ考えると、どうしても周囲の理解と協力が不可欠となります。
では、ゴミ屋敷火災を防ぐために、家族や近隣住民にはどんなことができるでしょうか?
ここでは、住人の心理・体調に配慮しつつ行えるおすすめの火災防止策を紹介します。
ぜひ参考にしてください。
■火元のリスクを優先的に減らす
一気に家全体を掃除・片付けするのが難しくても、火災リスクが高い場所を重点的に安全にすることで、火事の確率を大きく下げることができます。
・電気コードのほこり除去・断線の確認を一緒に行う
・ストーブやコンロの周りだけは物を置かないよう一緒に片付ける
・寝たばこ・調理中の離席をしないよう貼り紙で注意喚起
■火災予防の環境づくり
警報器や消火器は、火災時の「早期発見」「初期消火」に効果的です。
設置を負担に感じる場合は、行政・地域包括支援センターのサポートを利用できますよ。
・住宅用火災警報器を設置・点検する
・家庭用消火器を見えるところに設置する(使い方も一緒に確認してあげましょう)
・コンセントの数を減らし、タコ足配線を避けるよう提案する
■孤立を防ぎ、見守りの目をつくる
孤独や孤立は、ゴミ屋敷化・火災リスクの悪化につながります。見守り体制があるだけで、早期発見・介入が可能になり、万一の火災時にも助けやすくなるでしょう。
・定期的に声をかけ、ご近所のネットワークを作る
・民生委員・地域ボランティアに見守りを依頼する
限界を感じたら業者への依頼も検討

ゴミ屋敷の火事対策に取り組む中で、「自力ではもう限界かもしれない」と感じることは決して珍しくありません。
そんなときは、無理をせず、専門の業者に依頼することを考えましょう。
◆ゴミ屋敷専門業者に依頼するメリット◆
□安全面の確保
・ 可燃物や危険物の分別・処理を適切に行ってくれるので、火災リスクを大幅に軽減できる
・ 電気コード、ガス器具周辺の安全確保も同時に対応可能。
□精神的・肉体的負担の軽減
・ 自力では到底処理できない量でも、プロのスタッフが短時間で片付けてくれる
・ ゴミを処分する罪悪感やストレスを最小限に抑え、本人の心の負担も軽くなる
□再発防止への支援
・片付け後の整理整頓のアドバイスや、定期的な管理サービスを提供している業者もある
また、一部の自治体では、高齢者や障がいのある方、生活困窮者に対して、ゴミ屋敷の片付け費用を助成・支援する制度を設けています。
地域包括支援センターや社会福祉協議会を通じて、無料の片付け相談が受けられることもありますので、問い合わせてみるのもひとつの方法です。
限界を感じた時こそ、専門の力を借りるタイミングです。
安全で安心な生活環境を取り戻すために、業者や支援制度の活用も選択肢に入れてみましょう。
ゴミ屋敷清掃ならクリーンメイトへ

本記事では、ゴミ屋敷が火事になりやすいのはなぜ?出火原因5つと防止策について徹底的に解説という部分に焦点を当てて解説しました。
【内容まとめ】
・ゴミ屋敷火災が起きやすい主な原因(5つ)
・ゴミ屋敷になってしまう住人の心理的背景
・火災を防ぐための実践的な対策(本人以外も関与するのがポイント)
・難しい場合は、業者の力を借りる
現在悩まれている方にとって本記事の内容がお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。