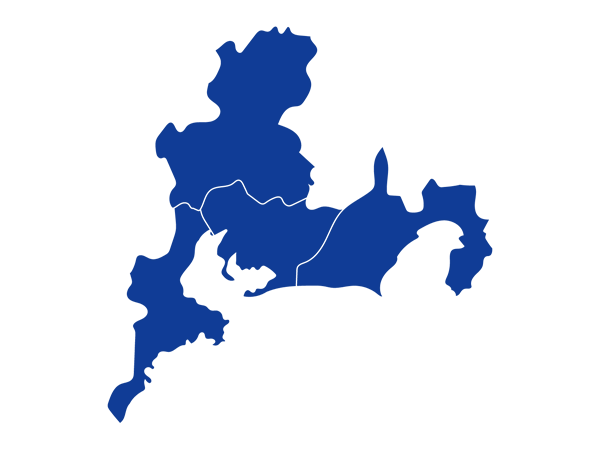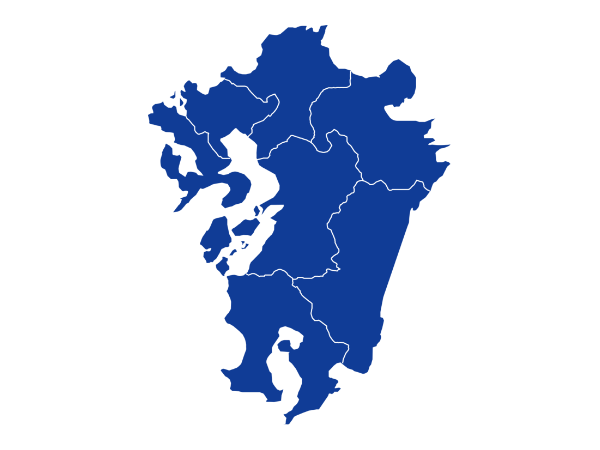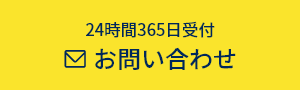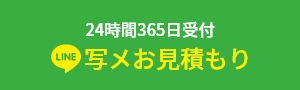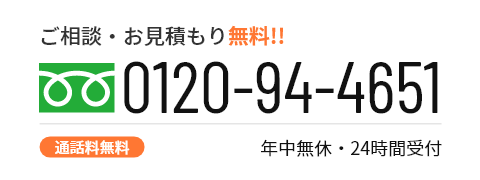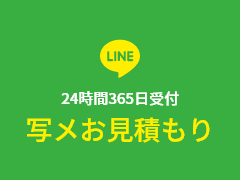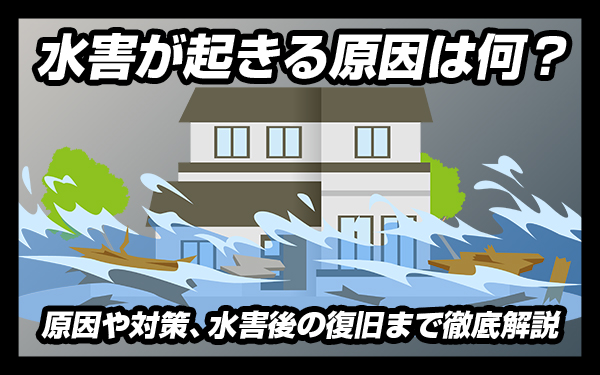
短時間に大量の雨が降る「線状降水帯」などの現象が頻発し、従来の治水対策では防ぎきれない被害が各地で発生しています。
本記事では、水害が起きる主な原因についてわかりやすく解説するとともに、被害を最小限に抑えるために私たちが取るべき対策について紹介します。
また、水害発生後に重要となる復旧の流れについても詳しく解説します。
水害の主な種類と発生要因

それぞれの特徴や起こる原因について、説明していきます。
■外水氾濫(がいすいはんらん)
川(河川)の水があふれて堤防を越えたり、決壊したりして、周囲に水が広がる現象
<<主な原因>>
・台風や豪雨などによる大量の雨で、河川の水位が急激に上がる
・ダムや堤防の決壊
・上流域での雨が下流に流れ込み、流量が増加
<<特徴>>
水の勢いが非常に強く、被害が大規模になりやすいです。
川の水が堤防を越えたり決壊したりすると、一気に大量の水が周囲に流れ出し、建物やインフラに大きな損害を与えます。また、河川からあふれた水は広範囲にわたって浸水を引き起こすため、住宅地や農地、道路などが一斉に被害を受けるおそれがあります。
<<被害が出やすい場所>>
・河川の近く
・川の下流域(特に大きな川の周辺)
・洪水を防ぐ堤防が弱い・低い地域
■内水氾濫(ないすいはんらん)
大雨で地面や排水設備が処理しきれず、都市や住宅地の中で水がたまってあふれる現象
<<主な原因>>
・短時間の集中豪雨(ゲリラ豪雨など)
・下水道や排水ポンプの能力不足
・川の水位が高くて、排水が川に流れない状態(逆流)
<<特徴>>
規模としては比較的小さいものの、私たちの身近な場所で発生しやすいという特徴があります。特に都市部では、短時間に大量の雨が降ると排水が追いつかず、道路や住宅地がすぐに冠水してしまいます。地下街や地下室などは水がたまりやすく、浸水被害を受けると復旧に時間がかかることも少なくありません。
<<被害が出やすい場所>>
・都市部や住宅地(特にアスファルトが多く、水が地面にしみ込まない場所)
・地形が低い場所(くぼ地、谷地など)
■土砂災害
大雨や地震などの影響で、山や斜面の土や岩が突然くずれ落ちる自然災害
<<主な原因>>
・大雨によって地盤が緩み、山や崖が崩れる
<<特徴>>
土砂災害は、大雨や長雨によって地盤がゆるみ、突然発生することが多いのが大きな特徴です。前ぶれがほとんどないまま、急に斜面が崩れたり、土石流が一気に流れ出すことがあり、避難が間に合わないケースも少なくありません。
特に夜間や雨の音で異変に気づきにくいときは、被害が大きくなる傾向があります。
また、土砂の流れに巻き込まれると、人命にかかわるほどの深刻な被害を引き起こすおそれがあり、非常に危険です。
<<被害が出やすい場所>>
・山間部
・急傾斜地
・川の近くにある崖下の住宅地
■高潮
台風や発達した低気圧が接近したときに、気圧の低下や強い風の影響で海面が異常に高くなる現象
<<主な原因>>
・台風や低気圧によって海面が異常に上昇し、海水が陸地に押し寄せる
<<特徴>>
満潮の時間帯と重なると、海面がさらに高くなり、堤防や防波堤を越えて浸水する危険性が一気に高まります。
そのため、住宅や商業施設、港湾エリアなどに甚大な被害をもたらすことがあります。
高潮によって海水が河川に逆流すると、川の水もあふれ出し、洪水と同時に発生する「複合災害」となることもあります。
<<被害が出やすい場所>>
・海岸沿いの低地
・港湾施設や河口付近
・海抜が0mに近い地域
水害被害を最小限に抑えるための対策

今すぐにできる水害対策としては、下記のようなものが有効です。
これらの対策は比較的短時間で取り組めるものばかりですので、是非実行してみてください。
■ハザードマップの確認
まずは、自宅周辺のリスクを把握することが重要です。ハザードマップを確認し、自宅が浸水想定区域にあるかを事前に調べおきましょう。
■排水溝や側溝の掃除
下水道の側溝や雨水枡は、定期的に掃除しておかないと詰まってしまいます。詰まった状態で水が流れ込むと、浸水につながるので危険です。
雨水がスムーズに流れるよう定期的に手入れしましょう。
■防災用品を準備
懐中電灯、非常食、飲料水、携帯充電器などの防災用品を準備しておくのはとても大切です。近隣住民と避難場所や避難経路を共有しておくことで、迅速な避難が可能になります。
なお、玄関などの開口部からの浸水を防ぐ方法としては、土のうで侵入口を塞いでしまう対策が一般的です。
土のうはホームセンターなどで売っているため、水害に備えて用意しておくことをおすすめします。
■避難場所・避難経路の確認
家族で避難先や避難ルートを共有しておきましょう。高齢者や子どもがいる場合は特に入念に。
水害復旧の方法
【1】安全確認と初期対応
■ 安全確保が最優先
水が引いたあとも、感電・ガス漏れ・建物倒壊の危険があるため、すぐには戻らず、行政や消防の指示を待ちましょう。
自宅に戻る際は、長靴・手袋・マスク・懐中電灯などを装備してください。
■ 被害状況の記録
損害保険や公的支援を受けるため、写真や動画で被害状況を記録します。(家の外観・室内・家具・家電など)
日付がわかるように撮影しておくとよいです。
【2】清掃・消毒・修繕作業
■ 家屋内の泥出し・清掃
まず、床下や家具の下にたまった泥を取り除きます。
家具や畳、カーペットなど吸水性のあるものはカビや感染症の原因になりやすいので、できる限り早く廃棄しましょう。
■ 乾燥と消毒
カビや細菌の繁殖を防ぐために、扇風機や除湿機を使って家屋をしっかり乾燥させることが必要です。
その後、消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで、床や壁を消毒しましょう。
■ 電気・ガス・水道の確認
感電防止のため、濡れた電気機器や配線には触れず、専門業者に点検・復旧作業を依頼しましょう。
【3】生活再建・各種手続き
■ 家財や住居の修繕
被害状況に応じて、業者に相談をしましょう。
修繕費用の一部は、保険や公的支援制度でカバーできる場合もあります。
■ 各種支援制度の活用
水害によって住まいや生活に大きな被害を受けた場合、国や自治体からの支援を受けることができます。
特に大規模な災害の場合は「災害救助法」が適用され、避難所の設置、食料や衣類の提供、応急仮設住宅の建設など、生活を立て直すためのさまざまな支援が受けられます。
■ 罹災証明書の申請
自治体に被害の程度を申請して、「罹災証明書」を取得することで、支援金や保険金の申請が可能になります。
水害からの復旧には、体力も時間も精神力も必要です。
しかし、国や自治体、地域、ボランティアなど、支援の仕組みは必ずあります。
困ったときは一人で抱え込まず、相談窓口や支援制度を活用しながら、段階的に少しずつ生活を立て直していくことが大切です。
水害復旧ならクリーンメイトにお任せください

本記事では、と水害が起きる原因は何?原因や対策、水害後の復旧までという部分に焦点を当てて解説しました。
【内容まとめ】
・水害の主な原因と種類 「外水氾濫」「内水氾濫」「土砂災害」「高潮」など
・被害を受けやすい場所の特徴
・水害対策としてできること 「ハザードマップの確認」や「避難ルートの共有」、「排水溝の掃除」や「土のうの設置」、「防災用品の準備」など
・水害後の初期対応と清掃
・生活再建と支援制度の活用
水害復旧でお悩みでしたら、プロである私たち業者にまずはお気軽にご相談くださいませ。
現在悩まれている方にとって本記事の内容がお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。