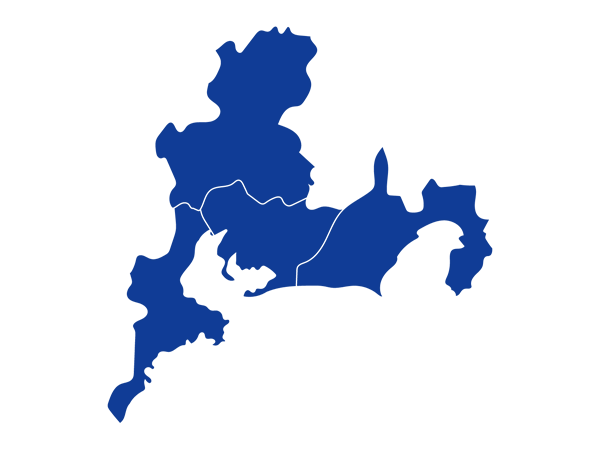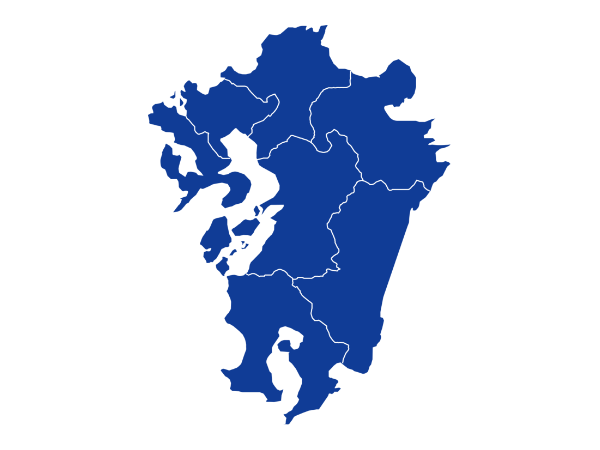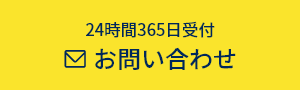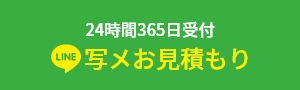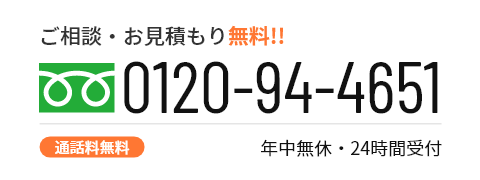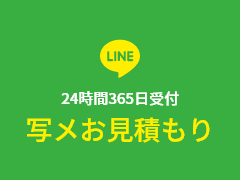マイホームを手に入れた後、多くの人が悩むのが火災保険や地震保険の加入です。
特に一戸建て住宅の場合、万が一の災害時に被る損害が大きくなりやすいため、適切な保険選びは重要でしょう。
しかし、いざ保険を選ぼうとしても「相場がわからない」のではないでしょうか?
本記事では、一戸建て住宅における火災保険および地震保険の相場について、わかりやすく解説します。
目次
地震保険と火災保険の保険料の決まり方

地震保険と火災保険それぞれの保険料の目安を知る前に、両者の保険の決まり方を理解しましょう。
地震保険と火災保険では保険料の決まり方が異なります。
■ポイント■
火災保険は自由設計型:補償範囲・金額・特約でカスタマイズ可
地震保険は制度型:政府が関与し、内容もルールも統一されている
という点です。
さらに詳しくみていきましょう。
<<火災保険の保険料の決まり方>>
*建物の構造
木造か鉄筋コンクリート造かなど
※木造は火災リスクが高く、保険料も高めになる
*建物の所在地
地域ごとの火災リスク、風水害リスクなどによって変動する
*建物の築年数・延床面積
築年数が古いほど保険料は高くなりがち
大きな建物ほど保険金額が高くなり、保険料も上がる
*保険の補償内容
火災だけでなく、風災・水災・盗難などを付けるほど保険料も上がる
*保険金額
補償額(建物・家財)が高くなるほど保険料も高くなる
*免責金額
自己負担額を設定することで保険料が安くなる場合がある
*保険期間
1年契約よりも、長期契約(5年・10年)の方が割安になることが多い
<<地震保険の保険料の決まり方>>
*建物の構造
火災保険と同様、木造は地震・火災の被害を受けやすいため保険料が高くなる
*建物の所在地(地震リスク)
各地域の「地震危険度」に応じて保険料が変わる
(全国で異なる料率が設定されている)
*保険金額
火災保険に対して最大50%まで設定可能
金額が高くなると保険料も高くなる
*保険期間
長期契約(最長5年)で一括払いにすると、保険料が割引になることがある
割引制度 建物の耐震性能に応じて「耐震等級割引」などの適用あり
(最大50%割引)
一戸建て地震保険・火災保険それぞれの相場

上記のことから、火災保険の保険料の目安は、年間約2万円〜5万円程度ではないでしょうか。
例えば、木造2階建て、延床面積100〜120㎡の住宅で標準的な補償を付ける場合、3万円前後になることが多いでしょう。
そして、地震保険の保険料は、火災保険の保険料の約10〜20%程度が目安です。
なので、年間1万円〜2万円前後と考えればよいでしょう。
火災保険と地震保険の違いを理解する

まず前提として、火災保険と地震保険は、どちらも住宅や家財を守る「損害保険」です。
火災保険は、火災・台風・豪雨・風災など、幅広い災害による損害を補償しますが、地震・津波・噴火は補償対象外です。
一方、地震保険は、地震・津波・噴火による被害に特化した保険ですが、単体では加入できず火災保険にセットして契約する必要があります。
両者には保険料の決まり方以外にも異なる点がありますので、項目ごとに詳しくみていきましょう。
補償対象が違う
保険会社によって異なる場合もありますが、両保険では補償対象が異なります。
【火災保険】
火災や落雷、風災、水害などによる建物や家財の損害を補償
※地震が原因の火災や倒壊などは補償対象外
【地震保険】
地震や噴火、これらによる津波を原因とする火災や損壊、埋没、流失などの損害を補償
加入方法の違い
先ほども触れましたが、地震保険単体の加入はできず、火災保険に付帯する形で契約しなければいけません。
支払われる保険金の仕組みや金額
【火災保険】
火災や風災、水害等が原因で生じた損害に対し、契約した保険金額の全額が支払われるのが一般的
【地震保険】
火災保険の30%から50%の範囲内で補償(法律で上限が決まっている)
損害の程度に応じて「全損」「半損」「一部損」の3段階で保険金が決定される
所得控除の対象かどうか
【火災保険】
所得控除の対象外
【地震保険】
「地震保険料控除」の対象
※毎年の確定申告や年末調整で控除を受けることが可能
このように、火災保険と地震保険は、それぞれ補完し合う性質を持っており、どちらか一方だけではカバーしきれないリスクも存在します。
リスクを幅広くカバーするためには、両方の保険に加入しておくことが大切です。
火災復旧ならクリーンメイトへ!

本記事では、一戸建ての火災保険と地震保険の相場っていくらくらい?という部分に焦点を当てて解説しました。
【内容まとめ】
・火災保険と地震保険それぞれの保険料の決まり方
・火災保険と地震保険一戸建て住宅の場合の相場
・火災保険と地震保険の違い
火災復旧についてお悩みでしたら、プロである私たち業者にまずはお気軽にご相談くださいませ。
現在悩まれている方にとって本記事の内容がお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。