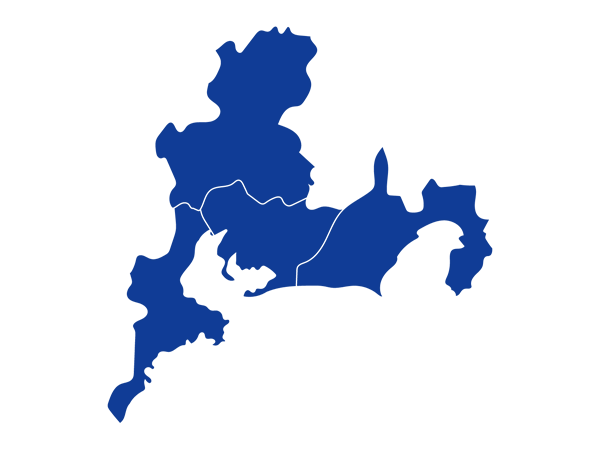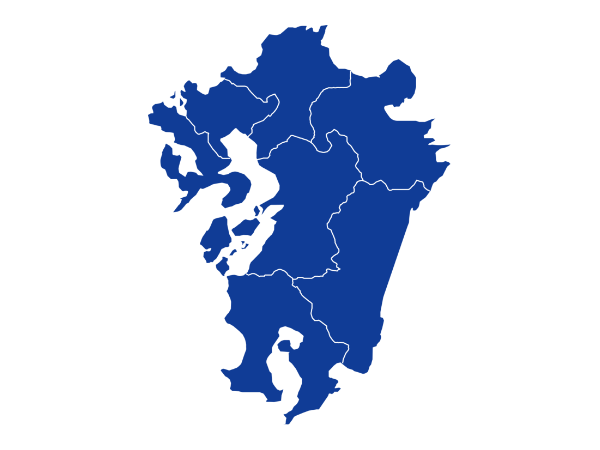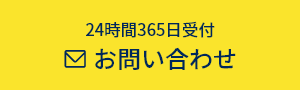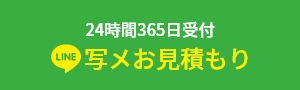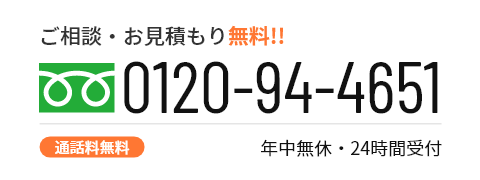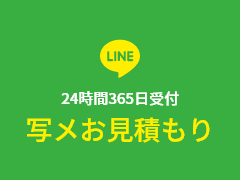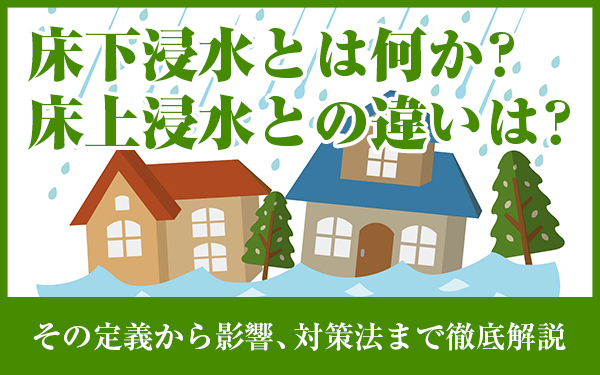
最近よく耳にする「床下浸水」という言葉ですが、具体的にどのような状態を指すのかご存じでしょうか?
また、よく似た言葉に「床上浸水」がありますが、違いは何なのでしょうか?
本記事では、「床下浸水」の定義や「床上浸水」との違い、そして万が一に備えた事前の対策法まで網羅的にご紹介します。
目次
床下浸水とは一体何か?

まずは床下浸水の基本からスタートしましょう。
床下浸水の定義と特徴
床下浸水とは
建物の床板より下の空間、いわゆる「床下」に水が入り込んだ状態のことで
浸水の深さが50cm以下の場合を言います。
見た目には大きな変化がないのが特徴です。
居住スペースまで水が上がらないため家具や家電への被害は少ないように見えますが、床下に水が溜まることで湿気がこもりやすくなり、カビや木材の腐食、シロアリの発生、悪臭などのトラブルが起こりやすくなります。
これを放置すると、家の土台や構造部材が傷み、将来的に住宅の寿命を縮めてしまう可能性があります。
床下浸水と床上浸水の違い
「床下浸水」とともによく聞く言葉に「床上浸水」がありますね。
床上浸水は
水が床板を超えて室内にまで入り込んだ状態のことです。
これは、家具や家電、内装などに直接的な被害を及ぼします。
生活空間が浸水してしまうため、衛生面の問題や復旧作業の負担が大きく、日常生活への影響も深刻です。
両者の違いをわかりやすくいうと、
床下浸水→「見えにくい被害」
床上浸水は→「生活を直撃する被害」
ということですね。
では、「床下浸水」と「床上浸水」日本で起こりやすいのはどっちでしょうか?
日本で起こりやすいのは 床下浸水 です。
国土交通省などの水害統計においても、床下浸水の件数は床上浸水の数倍に上ることがあり、
「床下浸水の方が発生頻度が高い」といえるでしょう。
その理由は、
日本の住宅地は、排水設備が整っており、家の造りにも工夫がされていることが多いため、大雨が降っても水が床の上まで入り込むことはある程度防がれているからです。
特に都市部では、道路の排水機能がしっかりしていることが多く、水位が上がってもまずは床下に水がたまりやすく、床上まで浸水するケースは比較的少ないのが現状です。
床下浸水の原因は何か?

ここからは床下浸水の原因やメカニズムについて詳しく解説します。
主な原因とそのメカニズムを知ろう
1. 集中豪雨や台風による大雨
原因
短時間に大量の雨が降ることで、排水しきれない水が住宅周辺に溜まる
メカニズム
雨水が排水溝や側溝からあふれ、住宅の基礎部分に流れ込みます。住宅が低地に建っている場合や、土地の勾配が家側に向いていると、特に水が集中しやすくなります。
2. 側溝や排水路の詰まり
原因
都市部では下水道が処理能力を超えると、水が逆流する
メカニズム
宅地内の排水口やマンホール、雨水桝などから水が逆流し、床下へ流れ込みます。排水管が詰まっていると、雨水や生活排水が逃げ場を失い、床下へ漏れ出すことも。
3. 地盤の低さや周囲との高低差
原因
川沿いや低地など、水が集まりやすい場所に住宅が建っている場合に起こりやすい
メカニズム
周囲より土地が低いため、雨水が自然に流れ込んでしまいます。土壌が水を吸収しきれないと、家の基礎周辺に水が溜まり、床下に侵入します。
4. 家の構造・施工不良
原因
防水対策が不十分だったり、基礎の立ち上がりが低い場合に起こりやすい
メカニズム
建物自体が雨水の侵入を防ぎきれず、隙間や亀裂、床下換気口から水が浸入します。特に築年数の古い家では、劣化による隙間からの浸水も多く見られます。
床下浸水を未然に防ぐ方法

先ほども少しふれましたが、日本で発生する水害は、「浸水被害」特に「床下浸水」が多いです。
人的被害(けがや死亡)よりも、住宅や建物への浸水による被害が圧倒的に多く、多くの家庭で生活や経済活動に長期的な影響をもたらしています。
こうした現実をふまえると、命を守るだけでなく、日常の暮らしを守るためにも、浸水への備えを強化することが非常に重要だといえるでしょう。
ここからは、誰にでもすぐできる事前の対策方法や避難準備を紹介します。
住まいを浸水から守るための事前対策
自宅の排水路・側溝の清掃と点検をしましょう
落ち葉やゴミ、泥などで排水路が詰まっていると、雨水があふれて床下に流れ込む原因になります。
→ 定期的に側溝や排水口を掃除し、水の流れを確保しましょう。
敷地の傾きや排水の見直しを
家の周囲が低くなっていたり、地面が住宅側に傾いていると雨水が集まりやすくなります。
→ 家の周囲に透水性の高い砂利や砕石を敷くと、水が地面に吸収されやすくなり、表面を流れる水の量を減らすことができます。
防水・止水アイテムを活用しよう
大雨が予想されるときには、簡易的な止水グッズで水の侵入を防ぐことができます。
以下のようなアイテムを事前に準備しておくとよいでしょう。
・土のう(簡易水のう)
土のう(土嚢)とは、土を詰めた袋で、水の侵入を物理的に防ぐシンプルな止水アイテムです。
玄関、通気口、敷地の出入口など、水が入りやすい箇所に積んでバリケードを作ります。
・止水板
止水板とは、アルミや樹脂でできたパネル状の防水板です。
玄関や車庫などの入り口に取り付けることで水の侵入を遮断します。
・防水シート
床下の通気口や換気口、窓枠のすき間などを一時的に覆って水の侵入を防ぐために使います。
通気口に水が入りそうなとき、ガムテープやサンドバッグで押さえつけるように貼ったり、雨どいの漏れや側溝のあふれ対策としても応用できます。
※ただし、換気を妨いでしまうため、常時ふさがないように注意しましょう。
避難準備も忘れずに行いましょう
地域のハザードマップを確認しましょう
浸水リスクがある地域を事前に把握しておくことで、早めの避難や対策につながります。
特に梅雨や台風シーズン前には、チェックするようにしましょう。
■非常持ち出し袋を準備しよう
|
□飲料水 |
|
| □非常食 缶詰や乾パン、エネルギーバーなど。火を使わずに食べられるものが便利 |
|
| □懐中電灯と予備の電池 停電時の必需品 手回し充電式やLEDタイプがおすすめ |
|
| □常備薬・救急セット 普段飲んでいる薬や、絆創膏・消毒液など □スマートフォンの充電器やモバイルバッテリー 緊急連絡や情報収集に必要 |
|
| □現金 停電でカードが使えない場合に備えて 小銭も含め準備 |
|
| □マスクや消毒液 感染症対策として |
※その他
携帯ラジオ、予備の衣類、タオル、ビニール袋、重要書類のコピー(保険証、身分証明書など)、
カッターやライターなどを用意しておくと安心です。
浸水の被害を受けたときは、無理に自分だけで対応しようとせず、状況に応じてプロの業者に頼ることも考えてみましょう。安全に復旧するには、専門的な知識や経験が必要になることもあります。
水害復旧ならクリーンメイトにご依頼を

本記事では、床下浸水とは何か?床上浸水との違いは?その定義から影響、対策法まで徹底解説という部分に焦点を当てて解説しました。
【内容まとめ】
・床下浸水とは?床上浸水との違い
・下浸水が起こる主な原因とメカニズム
・事前にできる床下浸水の対策
水害復旧でお悩みでしたら、プロである私たち業者にまずはお気軽にご相談くださいませ。
現在悩まれている方にとって本記事の内容がお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。