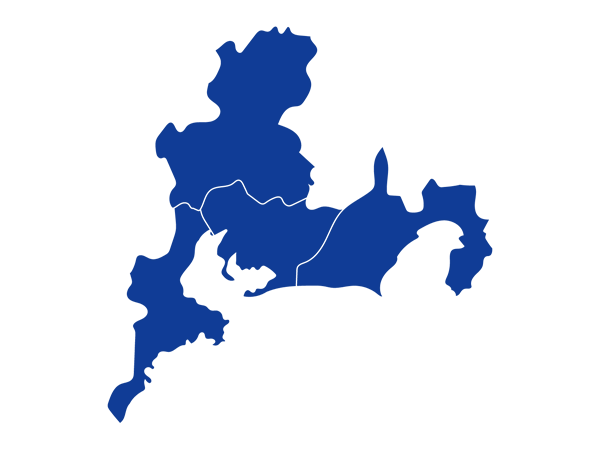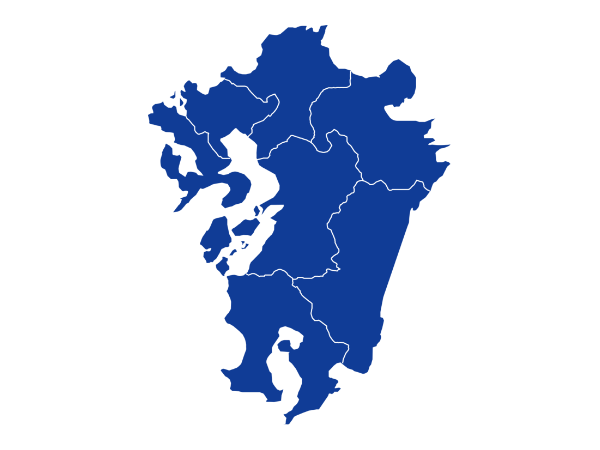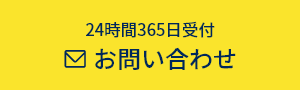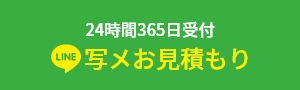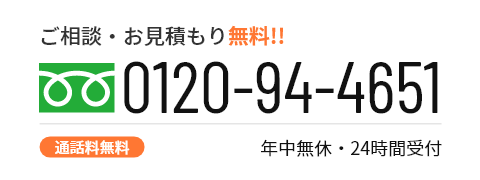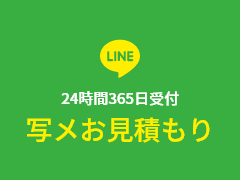台風や豪雨による河川の氾濫、土砂災害、浸水被害などの自然災害は予測が難しく、いつ誰の身に起こっても不思議ではありません。
そんな万が一の事態に備える手段の一つが、火災保険に付帯される「水災補償」です。
しかし、「水災補償」と聞いても、どのようなケースで補償されるのか、また補償の対象や条件について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、水災補償の補償内容や請求方法等について詳しく解説します。
目次
水災補償の対象となる損害

水災補償は、火災保険の中でも台風・豪雨・洪水・高潮などによる水害で被った損害に対して補償を行うものです。
具体的にどんなものが補償されるのか詳しくみていきましょう。
建物に対する補償内容
火災保険における「建物」とは、居住する住宅そのもの(外壁・屋根・柱・床・窓など)や、建物に付属する設備(キッチン・浴室・トイレなどの設備、給排水設備など)を指します。
▼ 補償される主な損害例
・台風や豪雨による床上浸水で建物の内装・設備が損傷した
・河川の氾濫で住宅が半壊・全壊した
・土砂崩れで建物が埋没・流失した
・高潮による海水の流入で建物が損害を受けた
保険金額や評価方法によりますが、上記のような損害が出た場合、修理費用や再建費用の一部または全額が保険金として支払われます。
補償されるのは建物だけか?
では、補償されるのは建物だけなのでしょうか?
実は、火災保険の水災補償は、「建物」に対してだけでなく、「家財(家具・家電など)」に対しても補償される可能性があります。
※ただし、家財は自動で補償されるわけではなく、契約内容によって異なるため注意が必要です。
多くの火災保険は、契約時に補償対象を選ぶ仕組みになっています。
水災補償も同様で、「建物のみ補償」「家財のみ補償」「建物+家財の両方補償」という契約形態があります。
家財に対する補償は、加入していない人も多いため、ご自身の保険契約がどうなっているか、内容を一度確認しておきましょう。
家財に対する補償内容
上記のことから、家財の損害も保険でカバーしたい場合は、家財補償をつける必要があるということがわかりましたね。
では、家財の補償をつけている場合、どんなものが補償されるのかを具体的に見ていきましょう。
ちなみに「家財」とは、建物内にある家具・家電・衣類・日用品・貴重品など、生活に使う動産類を指します。
▼ 補償される主な損害例(家財の補償もつけている場合)
・床上浸水により家具や家電が水没・故障した
・洪水や土砂で衣類・寝具などが使用不能になった
・地下室や1階に置いていたピアノや貴重品が浸水した
家財補償をつけていれば、
このような家財の損害に対して、修理費用や再取得費用が保険金として支払われます。
※保険金の支払いには「損害割合」や「被害状況の写真提出」などの条件があります。
水災補償の支払要件

では、火災保険の水災補償をつけていれば、すべての水に関する損害が自動的に補償されるのでしょうか?
そうではありません。
保険金が支払われるためには「支払要件」が定められています。
ここでは、補償が受けられるケースと受けられないケースをそれぞれわかりやすく解説します。
補償が受けられるケース
火災保険の水災補償が適用されるには、以下のような条件を満たす必要があります。
◆床上浸水した場合(地盤面から45cm以上の浸水)
建物の1階の床を超える高さまで浸水した場合は、水災補償の対象です。
※地盤面(地面の高さ)から45cm以上の浸水が目安とされることが一般的です
◆損害の割合が30%以上の場合
建物や家財の時価に対して損害額が30%以上になると、保険金が支払われます。
◆土砂崩れや洪水で建物が流失・埋没した場合
台風や集中豪雨により、土砂が家に流れ込んだり、建物が押し流されたりした場合にも補償対象となります。
◆高潮や河川の氾濫による水害
海水の流入や川の氾濫などによって建物・家財に損害が生じた場合も、水災補償が適用されます。
補償が受けられないケース
水による損害であっても、主に以下のようなケースでは補償が受けられない、もしくは制限される可能性があります。
◆地震による津波・土砂被害
津波による浸水や建物の流失、家財の損壊といった被害は、火災保険では補償の対象外となります。これは、津波が「地震による災害」として分類されているためです。
同じように土砂崩れに関しても原因によって火災保険の補償対象になるかどうかが変わります。
台風や大雨による土砂災害ではなく、地震が原因の場合火災保険では補償されません。
◆損害の程度が軽微な場合(30%未満)
建物や家財の損害額が小さく、全体の30%未満の損害にとどまる場合、補償の対象外になることがあります。
◆水漏れ(給排水設備の故障など)
給水管の破裂や、洗濯機の水漏れによる損害は「水災」ではなく、「水濡れ補償」の対象になります。水災補償の対象外です。
※また、そもそも水災補償をつけていない場合も補償対象外です。
水災補償の保険金請求方法

ここからは、実際に水災の被害を受けたときに、保険金をどのように請求すればよいのかについて、手続きの流れや必要な書類、注意点などをわかりやすくご紹介します。
請求手続きの流れ
水災による被害を受けたら、以下のステップで保険金請求を行います。
STEP1 被害発生
まずは、安全を確保したうえで、被害状況の写真や動画を記録しておきます。
浸水の深さ、損傷のある箇所、家財の状況などを可能な限り詳細に残すことが重要です。
STEP2 保険会社または代理店に連絡
被害を確認したら、すぐに加入している保険会社または代理店に連絡しましょう。
その際、以下を伝えるとスムーズです。
・被害の日時・状況
・建物や家財のどの部分が損傷したか
・被害の程度(例:床上浸水、家電が水没など)
STEP3 保険会社による調査
保険会社から損害調査員が派遣され、現地で被害の確認が行われます。
※軽微な損害の場合は、写真提出のみで対応されることもあり
STEP4 必要書類の提出
調査後、必要な書類を保険会社に提出します。(詳細は事項で)
STEP5 保険金の支払い
提出書類と調査結果をもとに保険会社が査定し、問題がなければ保険金が支払われます。
支払いまでは通常数日~数週間程度かかります。
必要書類と注意点
STEP4の際に提出する書類と注意点はこちらです。
【主な必要書類】
◆保険金請求書
保険会社所定の書式に記入(氏名・住所・契約内容・被害状況など)
◆被害状況の写真・動画
被災直後の建物や家財の状態を記録したもの
◆修理・交換にかかる見積書
リフォーム業者や電気店などから入手
(建物と家財の両方の見積もりが必要な場合もあり)
◆罹災証明書(必要に応じて)
被害の程度を証明する公的な書類
※市区町村の役所で発行される
◆本人確認書類
免許証、保険証など
【注意点】
◆被害の片付け前に写真撮影を忘れないこと
◆原状復旧前に保険会社へ連絡し、調査を受けること
◆家財の購入レシートや保証書などがあれば提出しておく
◆契約内容によっては免責金額(自己負担額)が設定されている場合もある
◆被害が軽微でもまずは相談しておくと安心(部分的に支払いがある場合も)
水害復旧ならクリーンメイトにお任せを

本記事では、火災保険の水災補償の範囲とは?補償内容について詳しく解説します!という部分に焦点を当てて解説しました。
【内容まとめ】
・水災補償は、台風・豪雨・洪水・土砂災害などによる損害を補償
・補償対象は「建物」だけでなく「家財」も選択可能
・水災補償が支払われるためには条件がある
・保険金請求は「写真・連絡・調査・書類提出」の流れ
水害復旧についてお悩みでしたら、プロである私たち業者にまずはお気軽にご相談くださいませ。
現在悩まれている方にとって本記事の内容がお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。