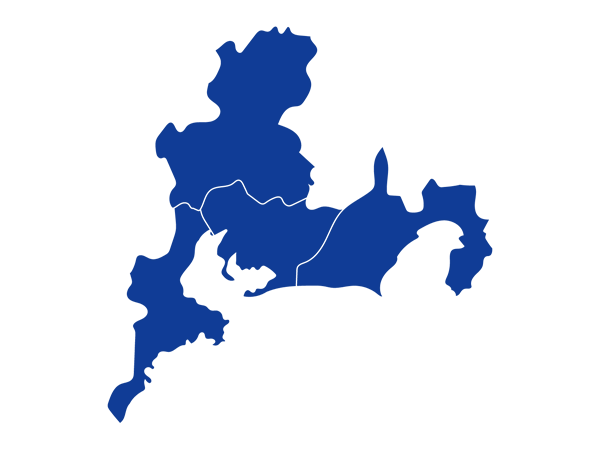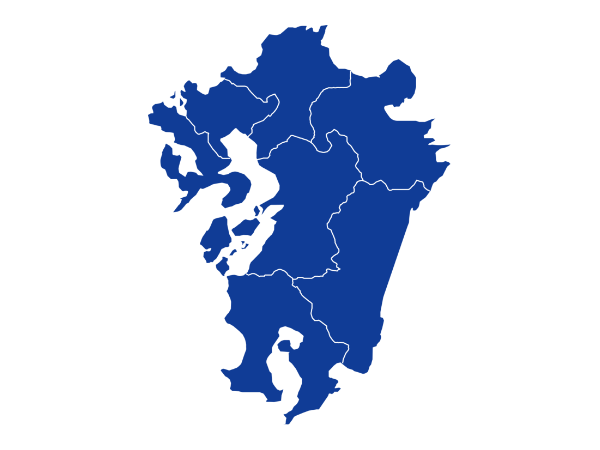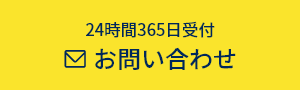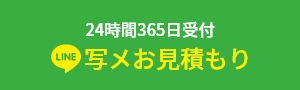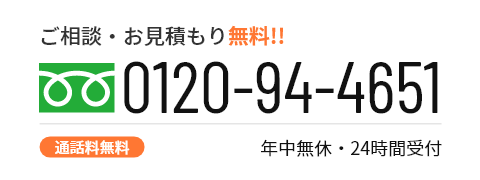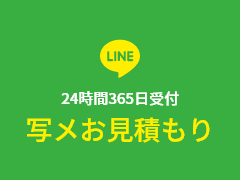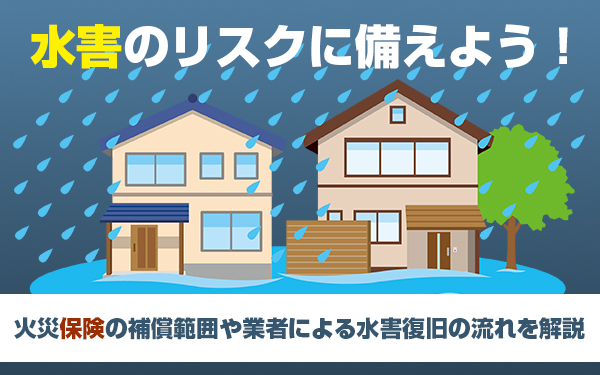
暴風雨、土砂災害、高潮等、突然の自然災害は私たちの暮らしに大きな影響を及ぼします。
住宅が浸水し、家財が損傷するケースも少なくありません。
こうした水害リスクに備えるためには、日頃からの防災意識とともに、適切な保険への加入や、万が一被害に遭った際の復旧方法を知っておくことが重要です。
特に火災保険は、火事だけでなく自然災害にも対応しており、水災補償を付けていれば、浸水や土砂災害などによる損害もカバーされます。
しかし、補償範囲や条件は保険会社や契約内容によって異なるため、事前に確認しておくことが必要です。
この記事では、火災保険における水災補償の基本、そして業者による水害復旧の一般的な流れをわかりやすく解説します。
いざというときに慌てないためにも、今のうちにしっかりと備えておきましょう。
水害の原因

水害の原因には大きく 「外水氾濫(がいすいはんらん)」 と 「内水氾濫(ないすいはんらん)」 の2つがあります。
それぞれの違いと特徴を、わかりやすく説明していきます。
■外水氾濫(がいすいはんらん)
川(河川)の水があふれて堤防を越えたり、決壊したりして、周囲に水が広がる現象
▼主な原因
・台風や豪雨などによる大量の雨で、河川の水位が急激に上がる
・ダムや堤防の決壊
・上流域での雨が下流に流れ込み、流量が増加
▼被害が出やすい場所
・河川の近く
・川の下流域(特に大きな川の周辺)
・洪水を防ぐ堤防が弱い・低い地域
▼特徴
水の勢いが非常に強く、被害が大規模になりやすいです。
川の水が堤防を越えたり決壊したりすると、一気に大量の水が周囲に流れ出し、建物やインフラに大きな損害を与えます。また、河川からあふれた水は広範囲にわたって浸水を引き起こすため、住宅地や農地、道路などが一斉に被害を受けるおそれがあります。
■内水氾濫(ないすいはんらん)
大雨で地面や排水設備が処理しきれず、都市や住宅地の中で水がたまってあふれる現象
▼主な原因
・短時間の集中豪雨(ゲリラ豪雨など)
・下水道や排水ポンプの能力不足
・川の水位が高くて、排水が川に流れない状態(逆流)
▼被害が出やすい場所
・都市部や住宅地(特にアスファルトが多く、水が地面にしみ込まない場所)
・地形が低い場所(くぼ地、谷地など)
▼特徴
規模としては比較的小さいものの、私たちの身近な場所で発生しやすいという特徴があります。特に都市部では、短時間に大量の雨が降ると排水が追いつかず、道路や住宅地がすぐに冠水してしまいます。地下街や地下室などは水がたまりやすく、浸水被害を受けると復旧に時間がかかることも少なくありません。
水災による被害と火災保険の関係

■火災保険とは?
火災による損害を補償する保険ですが、実はそれだけではありません。
多くの火災保険では、火災だけでなく、風災・雹災・雪災・水災などの自然災害による被害も対象とすることができます。
■火災保険の水災補償とは?
すべての火災保険に水災補償が含まれているわけではありませんが、
火災保険のオプションや基本補償に「水災補償」が含まれている場合は、以下のようなものがカバーされます。
■水災補償でカバーされる主なケース
・台風や大雨で床上浸水した
・河川の氾濫で建物が水につかった
・土砂崩れで家が損壊した
・大雨による地盤の沈下や傾き など
■補償の対象となるもの
・建物本体(住宅)
・家財(家具・家電など) ※加入時に家財も対象にしている場合に限ります。
■□注意■□
すべての火災保険に水災補償が含まれているわけではありません。
水災補償を外すことができるプランもあるため、契約内容を確認することが大切です。
次項では水災補償が受けられないケースについて詳しく解説します。
水災補償が受けられない主なケース
■水災補償を契約時に外している場合
最近の火災保険では、水災補償をオプション扱いにしているプランもあります。
例えば、高台やマンションの高層階など、水災リスクが低い地域の契約者が保険料を抑えるために水災補償を外している場合、水害に遭っても補償は受けられません。
■浸水の被害が軽微で、保険の支払い条件を満たしていない場合
多くの保険では、以下のような条件を満たさないと保険金が支払われないことがあります。
・床上30cm以上の浸水
・建物または家財の損害額が時価の30%以上
軽度な被害(床下浸水、家具の一部破損など)は補償の対象外となる場合があります。
■地震による津波・土砂被害
津波による浸水や建物の流失、家財の損壊といった被害は、火災保険では補償の対象外となります。これは、津波が「地震による災害」として分類されているためです。
そのため、津波による損害に備えるには、火災保険とは別に地震保険に加入しておく必要があります。
同じように土砂崩れに関しても原因によって火災保険の補償対象になるかどうかが変わります。
台風や大雨による土砂災害ではなく、地震が原因の場合火災保険では補償されません。
■経年劣化や施工不良による浸水
保険はあくまで「突発的・偶然な事故」を対象としています。
古くなった雨どいや屋根の不具合、施工ミスによる雨漏りなどは、多くの場合対象外です。
■建物の用途や使用状況が契約と異なる場合
契約上は住宅用としていた建物が、実際には事業用や空き家だった場合、保険金が減額されたり支払われないことがあります。
■保険契約者が故意に損害を発生させた場合
故意にドアや窓を開け放したままにしていたなど、明らかな過失や意図的な行為が認められると、補償の対象外になります。
■□まとめ■□
火災保険の水災補償は非常に心強い制度ですが、「加入していれば必ず補償される」とは限りません。
契約内容や補償条件をしっかり確認し、必要であれば見直しや特約の追加を検討することが大切です。自宅の立地やハザードマップの情報も活用して、補償の必要性を判断しましょう。
関連記事
床下浸水の放置は危険!災害や漏水が起きた後の対処法から特殊清掃の費用相場まで解説
業者による復旧作業の流れ

万が一、水災被害にあってしまった場合、被害の状況によっては専門業者による対応が必要となるケースもあります。
ここでは、業者による水害復旧の様子を紹介します。
【弊社クリーンメイト施工】
・施工内容:水害復旧 和歌山県
・ご依頼内容:大雨により近くの川が氾濫、ある程度の水は引き上げたが、床下に汚水・汚泥が残っている。汚れと臭いをどうにかしたい…!
■状況
・床下に残っている汚水・汚泥は10㎝ほどの高さ
・相対湿度を計測したところ90%以上湿度で飽和
・一度に大量の土砂や汚水が流出したため、床面上部にはその汚れが付着
■□ポイント■□
水害が起こってから48時間から72時間以内にカビは発生してしまいます。
日数が経過すればするほど、カビに起因する肺炎などの健康被害のリスクも高くなります。
<<作業の流れ>>
※作業前に水分量・湿度をチェック
↓
①汚水・汚泥吸い上げ
床下に残っている汚水をすべて吸い上げ、水気がない状態にします。
↓
②洗浄
泥を高圧洗浄バキュームで洗浄。
↓
③除湿・乾燥
機材を用いて床下全体の湿度を下げ、乾燥していきます。
↓
④カビ除去
汚水や汚泥によって発生したカビ菌を除去します。
↓
⑤消毒剤散布
しっかりと乾燥させた上で再度消毒剤を噴霧することにより、乾燥滞留菌を不活化させます。
【プロの技!】
作業中には床下天井の部分に数か所カビの付着が見られましたので、そちらも汚泥と同様に綺麗に洗浄して洗浄後にはカビ除去剤を塗布しました。
※カビ除去剤を付着面に塗布することで、真菌の増殖を抑える効果があります。
↓
①汚水・汚泥の吸い上げ、②洗浄、③除湿・乾燥 の作業を経過を見ながら数回行います。
↓
計1週間ほどの日程で全体の作業が終了
作業範囲:床下(80㎡)
作業人数:8人
作業時間:約120(乾燥時間も含む)時間
作業金額:650,000円(税込)
その他の作業実績はこちら
特殊清掃のことならクリーンメイトにお任せください

本記事では、水害のリスクに備えよう!火災保険の補償範囲や業者による水害復旧の流れを解説という部分に焦点を当てて解説しました。
【内容まとめ】
・水害の主な原因は「外水氾濫」と「内水氾濫」
・火災保険には水災補償を付けられるが、契約内容によって補償の有無が異なる
・火災保険の補償を受けられない主なケースにも注意が必要
・実際の水害復旧作業には専門業者による迅速かつ徹底した対応が必要
水害復旧についてお悩みでしたら、プロである私たち業者にまずはお気軽にご相談くださいませ。
現在悩まれている方にとって本記事の内容がお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。